文化とまち、深く考察 故吉田光男さん随筆集刊行 水戸芸術館設立に尽力 「功績伝える一助に」 茨城

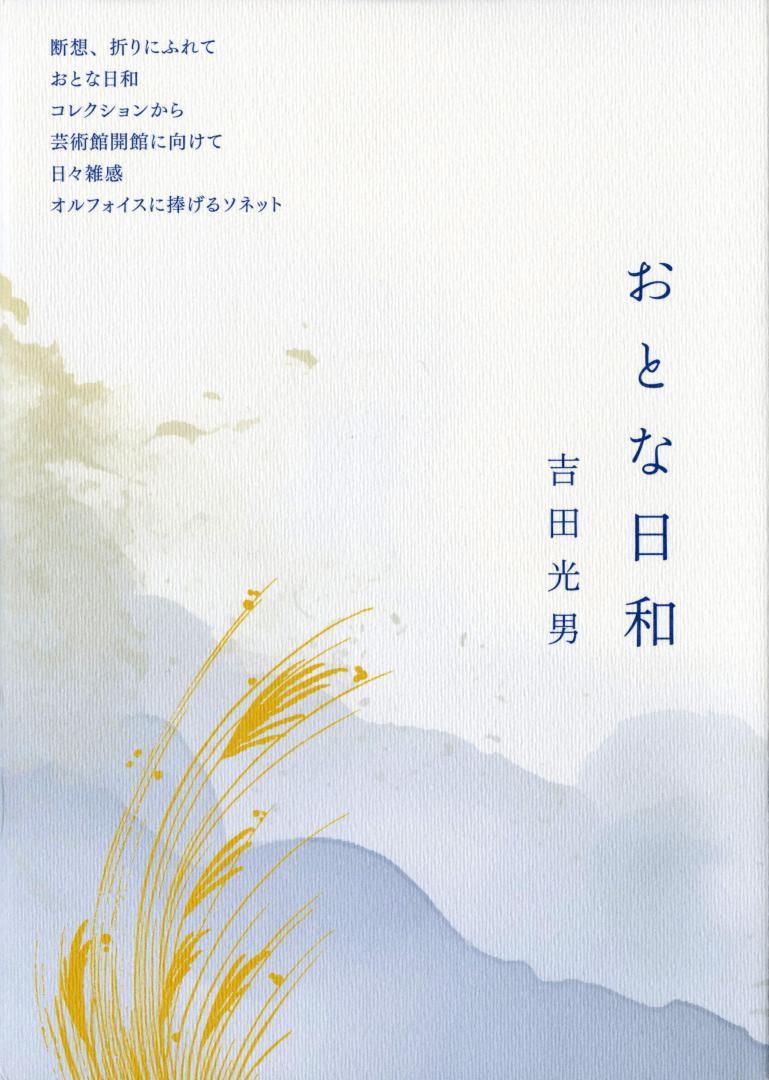
水戸芸術館(茨城県水戸市五軒町)の設立に尽力した水戸市芸術振興財団元副理事長、吉田光男さん(2022年、89歳で死去)の随筆集「おとな日和 吉田光男」を、交流があった人たちが刊行した。文化とまちづくりをテーマにした深い考察などが機微に富んだ文章でつづられている。関係者は「吉田光男さんは表に出ることなく、水戸の芸術文化の振興に力を注いだ方。功績や人柄を広く伝える一助に」と話している。
吉田さんは1932年、水戸市生まれ。実家は灯油や船の燃料を扱う石油店を営む。県立水戸一高時代は文学の研究者を志すが、家業を考慮して東京大経済学部に進学。ただ文学への夢を諦めきれず、同大を卒業後、京都大大学院文学研究科に進む。その後、父親の急逝により、57年に中退し、翌58年に26歳で会社を受け継いだ。
66年には水戸青年会議所理事長に選出された。若手経営者などと仕事を超えて、水戸のまちづくりについて議論を重ねたという。
70年代になると、企業のトップが名を連ねる自身の親睦グループに、後に水戸市長となった8歳下の佐川一信さん(1940~95年)が加わる。吉田さんは文化振興をまちづくりの柱に据える佐川さんの政治哲学に共感。84年の市長選で後援会長を務め、佐川さんを支えた。
佐川市政2期目の目玉となった同館設立では、90年の開館を控えた88年に運営を担う財団の副理事長に就任。佐川さんと二人三脚で、初代館長となる評論家の吉田秀和さん(1913~2012年)を招請するなど、同館の下地づくりに取り組んだ。
随筆集刊行の話が持ち上がったのは昨秋。吉田さんの友人たちが「芸術文化を愛した故人の思いを形に残すべき」と遺族などに呼びかけた。今年1月、生前に書き記した主な文書がそろい、吉田さんと40年近く親交があった財団常務の大津良夫さん(70)が、遺族と出版社の間に入って編集作業に関わった。
内容は文化と水戸のまちについての考察のほか、同館誕生の裏話や生活情報誌で連載したエッセイ、陶磁器を主とした骨董(こっとう)収集の話題など幅広い。巻末には1957年に京都大ドイツ文学科に提出した学位論文を収録した。
大津さんは「吉田さんは水戸が生んだ知の巨人。だが決して表には出ず、水戸芸術館誕生の立役者となった。その存在を多くの人に知ってもらいたい」と話す。
「おとな日和 吉田光男」は309ページ。販売されず、市内の図書館などで読むことができる。同財団(電)029(227)8111。
















