火災検知AI、精度向上 大洗町消防導入7カ月 夜間、空き家の監視補完 茨城

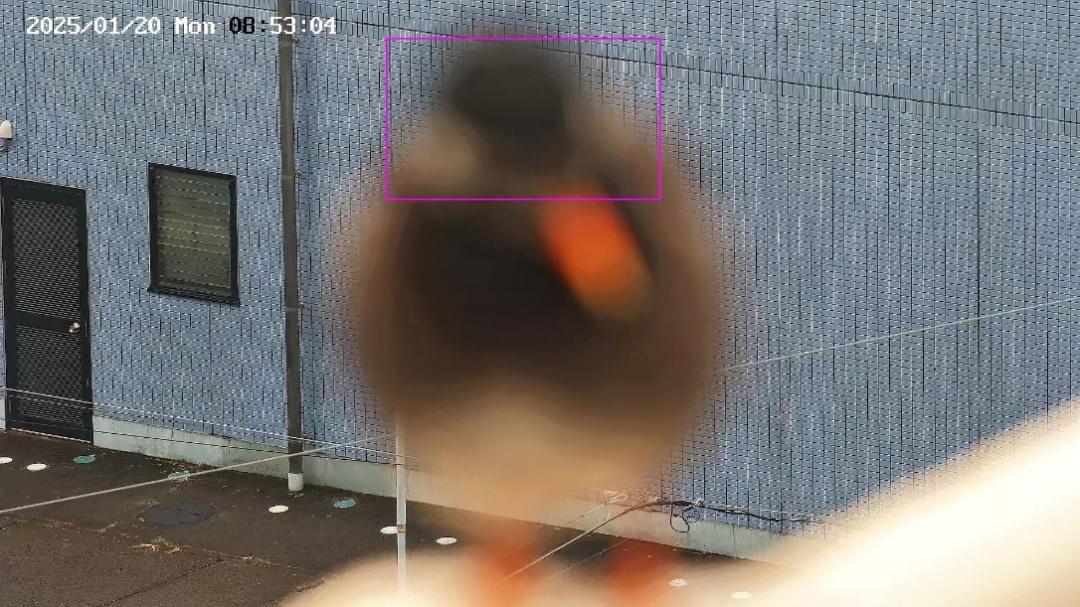
迅速な火災発見、消火活動につなげようと、茨城県大洗町消防本部(同町磯浜町)が火災を自動で検知するシステム「火の見櫓(やぐら)AI(人工知能)」を導入し、本格始動してから約7カ月たった。これまでに2件の煙を正常に検知するなど一定の成果が見えた。鳥や車のライトを煙や炎と誤って検知する「誤検知」も確認されているが、その都度、課題を洗い出している。
同システムは、発見が遅れがちな空き家や夜間の火災を素早く把握する目的で昨年11月に導入し、今年1月から本格運用を始めた。
地上18メートルの同本部訓練棟最上部に設置されたカメラが、半径800メートルを24時間体制で撮影。映像をAIが分析し、火災と認識すると、同本部の通信指令室にあるモニターに映像が表示され、隊員に異常を知らせる仕組みだ。
同2月には住宅街の煙を2件検知し、隊員が現場に駆け付けた。いずれも住民による野焼きと判明し、火災ではなかったが、迅速な消火と注意喚起につながった。同本部は「煙を検知したこと自体が早期覚知といえる。それによって被害を抑えられるのなら導入した意義は大きい」と話した。
一方、ぼやけた鳥の影を煙と検知したり、車のテールランプを炎と検知したりする「誤検知」も確認されている。同システムを開発したアースアイズ(東京)によると、煙のうち、工場の煙など火災以外の煙を「目的外検知」とし、鳥や光の反射、車のライトなどを検知すると「誤検知」として分類される。いずれのケースも同本部から同社へ速やかに報告され、改善処置が取られた。
同社は「誤検知を減らすためには発報データを精査して繰り返しAIに学習させることが必要」と強調。その上で「四季によって町の色合いも変わる。町の特性を理解するところから1年間学習して、AIも一人前になる」とする。
本格始動から約7カ月、誤検知報告と改善を行った結果、「確実に精度は高まっている」と同社。同2月に100回近くあった誤検知は、現在は1カ月に1回程度まで減ったという。
同システムについて、同本部は「119番通報よりも早く、夜間や空き家など人目の少ない場所の『監視』を補完してもらえるのは助かる」と評価し、「人の目には限界がある。われわれの活動の補助になるようなAIカメラになってほしい」と、さらなる精度向上に期待を寄せている。
















